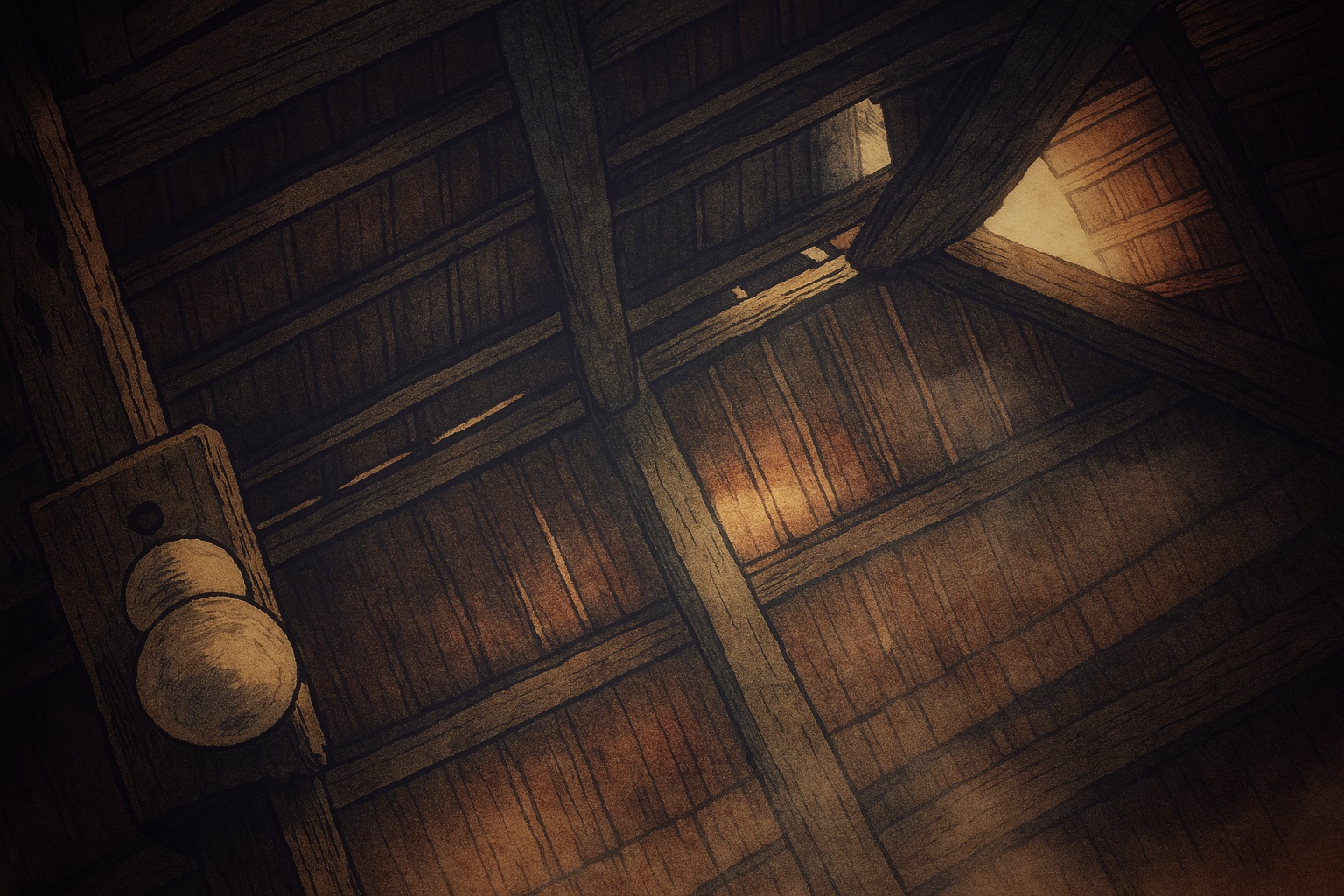──Based on “屋根裏の散歩者” by 江戸川乱歩
書庫開扉
貴女御殿 幻想書庫へ、ようこそ。
私はこの書庫をご案内いたします管理人——玻瑠(はる)と申します。
ここには、世界中から失われゆく幻想の記憶、
誰にも知られずに終わった夢の断片、
語られることのなかった物語たちが静かに眠っております。
本日お見せいたしますのは、かつてこの国に生きたひとりの記録。
——“江戸川乱歩”と呼ばれた男が遺した、異形の幻想。
彼の綴った断章は、いまもなお、夢の底でわずかに震えております。
その一篇を、今宵は皆様にご覧いただきたく存じます。
どうぞ、お心のご準備を。
ご案内いたしますのは、『散歩者』。
それは、まだ東京に夜霧が残っていた頃——
朽ちかけた御殿の屋根裏に、“それ”は静かに住んでおりました。
【第一章:屋根裏の部屋】
その屋敷には、風がなかった。
蝉の声が遠く、時折カラスがひと鳴きして、また静寂。
灰色の雲が流れ、空の色が見えない。東京の外れ、忘れられたような町だった。
門扉の錆びた蝶番が、ぎいと軋む。
「……あの、この部屋……まだ空いてますか?」
若い男の声。細身の体に薄い麻の上着、片手に古い鞄を下げていた。
声をかけたのは、門の内側から様子を窺っていた女中だった。
「屋根裏の部屋でございますか? ……何も、ございませんよ?」
そう言って女中が開けた門の先には、
洋館と和館が継ぎはぎに組まれたような、不思議な造りの屋敷が建っていた。
外壁の一部は剥がれ落ち、蔦が這い上がっている。
木製の窓枠には、黴の痕と古い結露の跡がこびりついていた。
「何もないほうが、落ち着きます。」
男はそう言って笑ったが、目は笑っていなかった。
木の階段は、歩くたびにぎいと鳴いた。
壁には、和紙の剥がれかけた掛け軸と、洋風の花瓶。
そして、その横には無表情な日本人形が置かれていた。
時代も趣もごちゃ混ぜに詰め込まれた屋敷は、まるで夢の中の構造物のようだった。
「こちらです……屋根裏へ上がる階段は急でございますので、どうかお気をつけて。」
女中が照らす行灯の明かりが、天井に影を揺らす。
その奥に見えたのは、年季の入った狭い梯子だった。
男は一段ずつ音を立てながら登っていった。
ふいに、後ろを振り返る。
しかし女中の姿は、もうそこにはなかった。
屋根裏部屋には、窓がひとつだけ。
夜の東京を斜めに切り取るように設けられた、小さなガラス窓だった。
そこから入る月の光だけが、部屋を満たしていた。
家具も飾りもない部屋。床も壁も天井も、ただの古びた木板。
だが——確かに、何かがいる。そんな気配が漂っていた。
「……私は、なぜここに来たんだ?」
男はポツリと呟いた。
まるで、その奇妙な気配に話しかけるように。
【第二章:気配と夢】
その晩、男はよく眠れなかった。
窓の外では、風のない空に雲がゆっくり流れていた。
時計の音もない。虫の音さえしない。
ただ、天井のどこかから——わずかに、軋むような音がしていた。
きぃ……、きぃ……。
「……ねずみか?」
男はそうつぶやいたが、自分でも信じていなかった。
その音には“間”があった。規則的すぎた。
まるで、誰かが——歩いているようだった。
その夜、男は夢を見た。
屋根裏の梁(はり)に、白い手がぶら下がっていた。
その手は、指先だけで男を指していた。
動かないのに、確かに見ていた。その“目”のような感覚が、男の背中に貼りついていた。
目が覚めたとき、部屋は暗かった。
月は雲に隠れ、窓の外は墨を流したように黒い。
男は立ち上がった。床板が軽く軋む。
ゆっくりと、窓に近づく。
窓のガラスに、何かが映っていた。
自分の顔——ではなかった。
朝になっても、その影のことは、思い出せなかった。
「お湯は一階にございます。洗面所は奥でございます。」
女中の声は、昨夜と変わらぬ調子だった。
しかし彼女の目は、何かを図るように、男の顔を見つめていた。
「よく、お休みになれましたか?」
「ええ……まあ。」
男は、苦笑するしかなかった。
【第三章:我か彼か】
その日から、男は毎晩、屋根裏の窓辺に座るようになった。
書くことも読むこともせず、ただ、東京の夜を見下ろしていた。
窓の外には、人の形をした明かりが浮かんでは消えた。
誰かが傘を差し、誰かが立ち止まり、誰かが顔を上げた。
けれど、屋根裏部屋の中では——誰も、動いていないはずだった。
それでも男は、たしかに聞いていた。
きぃ……きぃ……と、床板を踏む足音。
ぴたり、と止まり、次の瞬間には、背後の空気がわずかに沈む。
まるで、誰かが自分の呼吸に合わせて歩いているような、そんな感覚。
ある夜、男は意を決して声を出した。
「そこに……いるんですか?」
沈黙。
……いや、違う。沈黙ではなかった。
聞こえてきたのは、笑い声のような呼吸音だった。
喉の奥でくぐもるような、湿った笑い。
「……あなたは、いつから……そこに?」
男の声が震えた。
言葉の途中で、自分が話している理由が分からなくなった。
声をかけた相手は、果たして他の誰かだったのか——
それとも、自分の中の何かだったのか。
次の日、男は町へ出た。
帽子を目深にかぶり、新聞を買い、喫茶店の窓辺に座った。
人の顔を見ると、妙なざわめきが胸の奥で広がる。
似ている。あの気配に。あの笑いに。
ふと、窓ガラスに映る自分の顔が、
昨夜、窓に浮かんだ“それ”と重なって見えた。
「……違う、違う……」
男は震える手で珈琲を飲んだ。
味がしなかった。
【第四章:鏡の中の男】
屋敷に戻った夜、男は鏡を見た。
屋根裏の部屋には鏡などない。
だがなぜか、今夜の壁の隅には、ひびの入った手鏡が立てかけられていた。
誰が置いたのか、いつからあったのか、覚えていない。
男は、そっとその鏡に近づいた。
鏡の奥には、男が映っていた。
いや、よく見ると——何かが違った。
目の焦点が、こちらを見ていない。
鼻筋がわずかに歪んでいる。
唇の端が、笑っているようで笑っていない。
男は目をそらした。
そして、もう一度だけ見直した。
今度は——何も映っていなかった。
その夜、夢の中で誰かが語りかけてきた。
「わしは、あんたや。」
声は男の声だった。
だが、どこか湿った響きで、何重にも重なっていた。
「ずっと、見てたやろ? 屋根裏から。あれ、わしや。」
「……お前は……」
「もう分かっとるやろ? わしは、ずっとここにおった。」
声がそう言ったとき、男の背中に、ぬるい手が触れた気がした。
首の後ろから、肩へ、肩から耳の裏へ。
その手は、まるで自分の手のようだった。
目が覚めた時、男の耳元にはまだかすかに声が残っていた。
「わしは、あんたの奥で生きてる。」
「見てるだけでは、もう足らんのや。」
【第五章:男のゆくえ】
夜、屋根裏の窓が開いていた。
開けた覚えはなかった。
月が真っ直ぐに差し込んでいた。
光は斜めに床を切り取り、部屋の片隅にもう一つの影を落としていた。
男は静かに立ち上がる。
影もまた、静かに立ち上がる。
男が右手を上げると、影も右手を上げた。
左を向くと、影も左を向く。
歩き出すと、影も歩き出す。
……だが、歩調が半拍だけ、ずれていた。
気づけば、男は部屋の隅にあった手鏡の前に立っていた。
月明かりの中、そっと鏡をのぞき込む。
「なんだ?これはいったい誰なんだ?」
鏡の中にいたのは、自分ではなかった。
それは、あの“関西弁の男”だった。
こちらをじっと見つめている。
笑っているようで笑っていない目。
そして、唇だけがにやりと歪んでいた。
男は声を上げようとした。
だが、からからに乾いた喉からは空気しか出なかった。
ぐらりと視界が傾き、身体が“何か”に引かれていく。
落ちていく。
鏡の奥へ、闇の底へ。
ふと、屋根裏の窓がきぃ……と音を立てて閉じた。
……
……。
「よく、お休みになれましたか?」
——聞き覚えのある声。女中だった。
男は目を開けた。
畳の匂い。旅館のような和室。
差し込む朝の光。
「……はい、ほんまに。こんなによう寝れたんは何年ぶりやろなあ。
悪い夢から覚めたような、ええ気分やわ。」
そう答えたのは、あの関西弁の男だった。
にやり、と笑ったその目は、空っぽだった。
まるで、長い長い眠りから解放されたもののように。
女中はほっとしたように微笑み、言った。
「それは、ようございました。」
そして立ち上がり、部屋を出ていった。
……
同じころ、屋敷の屋根裏。
窓はきっちりと閉じられ、鍵がかけられている。
誰もいないはずのその空間に、きぃ……と床が鳴った。
そして、小さな声が響いた。
「……ここは、静かで、落ち着くな……」
その声は、もう関西弁ではなかった。
あとがたり
今宵も、ひとつの記憶を読み終えてくださり、ありがとうございました。
見る者と、見られる者。
出る者と、取り残される者。
この世界には、ほんの少しだけズレた“境目”が存在いたします。
うっかりしていると、あなたもふとその“境目”に引き込まれてしまうかも知れません。
——では、今宵はこれまで。また次の記憶でお目にかかりましょう。
🔮次回予告
「次にご案内するのは、白布の下でまどろむ“芋虫の姫”。
その唇に微笑みはあるが、誰もその意味を知る者はいないのです。」